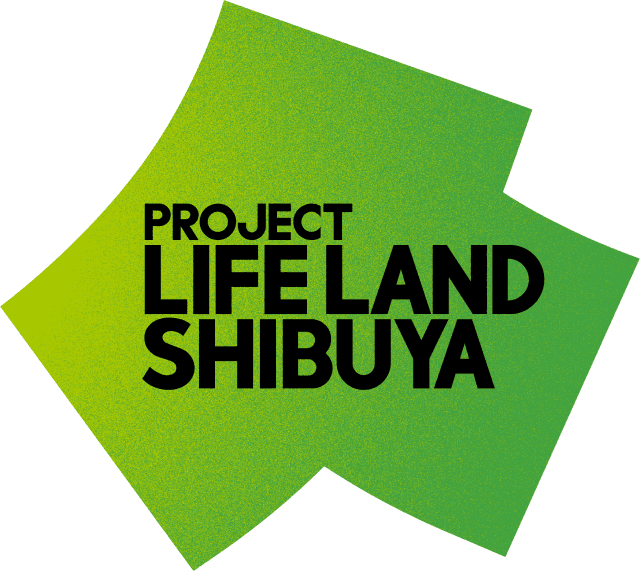桑田佳祐や吉澤嘉代子らのCDジャケット、雑誌『装苑』の表紙デザイン、ラフォーレ原宿の広告など、カルチャーとファッションの最前線で活躍するアートディレクター・千原徹也氏(れもんらいふ 代表)。2024年春に開業する東急プラザ原宿「ハラカド」では、ロゴデザインやクリエイティブラウンジのディレクションも手がける。

2023年7月、彼の初監督映画『アイスクリームフィーバー』が公開された。
クリエイターの夢をあきらめかけているアイスクリーム屋のアルバイトとして主演で務めるのは、日本映画界に欠かせない俳優として一層存在感を増しつつある吉岡里帆。物語の求心力となるミステリアスな作家を演じるモトーラ世理奈に加え、「水曜日のカンパネラ」のボーカル・詩羽、松本まりか、本作が映画初出演となる南琴奈、後藤淳平(ジャルジャル)、はっとり(マカロニえんぴつ)、MEGUMI、コムアイ、片桐はいり、安達祐実といった個性豊かなメンバーがそろう。
音楽は吉澤嘉代子が主題歌「氷菓子」を書き下ろし、エンディングテーマには小沢健二の名曲「春にして君を想う」を起用。オープニングテーマなど劇中の音楽は、田中知之(FPM)が担当するなど、映画、音楽、ファッションなど日本のカルチャーを形成するクリエイターが参加した。
加えて『アイスクリームフィーバー』の大きな特徴は、映画の枠を超えた他分野へのコラボレーション。ウンナナクール、猿田彦珈琲、アダストリア、PARCO、ボディファンタジー、グランマーブルといったブランドとの連動企画が同時展開し、「映画×ファッション×広告×デザイン」が融合したボーダレスなクリエイティブが実現した。
「映画監督が長年の夢だった」と語る千原徹也氏に、初作品『アイスクリームフィーバー』で挑んだクリエイティブの全容と、これからの展望を聞いた。

市川崑、ソール・バス、伊丹十三──人生を変えた映画の中のデザイン
─広告を中心としたアートディレクターとして活躍されてきた千原さんが、このタイミングで映画という新しい領域にチャレンジしようと思ったきっかけについてまずは教えてもらえますか?
千原徹也(以下 千原):いつか映画をつくりたいという気持ちは子供の頃からずっと持っていましたね。僕が小学生だった80年代はハリウッド映画黄金期で、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『E.T.』『スター・ウォーズ』に夢中になっていました。
その後、中学で市川崑の作品に出会い「映画の中のデザインって面白いな」と気づくようになった。高校生の頃にグラフィックデザイナーのソール・バスの作品集を読んで、彼のデザインした『サイコ』や『ウエスト・サイド物語』の仕事を見て影響を受けつつも、彼がミノルタ(現・コニカミノルタ)やコーセーなど有名な企業ロゴも手がけていることを知りました。
そこで「あ、これはグラフィックデザイナーという仕事なんだ」と職業を意識するようになって、だんだん憧れがデザインの方面にずれていったんです。
─元々グラフィックデザインに興味をもったきっかけが、映画であったと。
千原:あと、伊丹十三さんの影響も大きいです。商業デザイナーとしてマルチに活躍された伊丹十三さんが50歳を超えて初の監督作品の「お葬式」をつくっていて。
なので漠然と、僕も50歳ぐらいになったら今まで培ったクリエイティブの集大成として映画監督をやりたいという気持ちがあった。グラフィックデザインの領域である程度やりたいことができるようになってきたと感じ始めた43歳の頃に本格的にそれを考え始めて、現在47歳でそれを実現できたという経緯です。
─本作『アイスクリームフィーバー』にも、オープニングからエンドクレジットに至るまでアートディレクター・千原さんならではのタイポグラフィが存分に散りばめられていますね。
千原:僕もデザインをずっと生業にしてきた人間なので、やっぱりそこが映画監督としての自分の売りだろうなと。原作のタイトルである『アイスクリーム熱』を、『ICE CREAM FEVER』とポスターや劇中のタイトルクレジットで英語表記に変えたのは、デザインのしやすさやビジュアルを優先したかったからでもあります。
フランス語やロシア語が一部混ざっている特殊な英語表記デザインになっているんですが、 ソフィア・コッポラの初監督作品の『ヴァージン・スーサイズ』やウォン・カーウァイの『マイ・ブルーベリー・ナイツ』みたいに、タイポグラフィが記憶に残る映画にしたかった。僕が20代の頃にリバイバルブームでよく観た、ヌーヴェルバーグ作品からも同じように影響を受けています。
女性同士だからこそ紡がれる、「言葉にできない」完結しない感覚
─本作は千原さんが親交のある川上未映子さんの短編『アイスクリーム熱』が原作となっています。映画の中では原作のセリフにインスパイアされつつも、ストーリーとしてはオリジナルに近い形で世界観を広げていますね。
千原:川上さんには映画の企画をスタートする段階から相談していて。オリジナル脚本を元々は想定していたのですが、そこで僕がやりたいと考えていた「女の子の人生に焦点を当てて肯定する」「大きな事件が起きるのではなく、気持ちの変化によって世界の見え方も変わる」というイメージを伝えていたら、この『アイスクリーム熱』を川上さんから提案されて。読んでみて、確かにこの作品を映像として膨らましていくのは面白いものになりそうだと感じました。

─原作の『アイスクリーム熱』は、アイスクリーム屋で働く女性の主人公とそこに来店する男性客の関係が軸になっていますが、今回の映画ではそこが「女性と女性」の関係にシフトされています。ストーリーを推進する他の登場人物もほぼ女性という配役をされていますが、この意図とはなんでしょう?
千原:原作の川上さんや、僕が普段から考えていることや表現していることを総合していったら、自然と女の子同士の作品になっていきました。
僕と川上さんはウンナナクールという女性用下着ブランドの広告をずっと一緒にやっているのですが、その中で「女の子、登場」というコンセプト&コピーをつくったことがあって。そのクリエイティブをする際に、川上さんとは女性にまつわる様々な対話をしたんですよね。
例えば、白雪姫やシンデレラ、ディズニーでも女の子が主役の作品はあるけど、最後は男の王子様が全部救ってくれるのが当然のハッピーエンドになってること。「痴漢注意」のポスターが、男性に向けてではなく女性に向けて気をつけろと喚起していること。そういう男性上位、男性社会が大前提になっている“歪み”みたいなものを、川上さんと話す中で僕も勉強したり、考えたりして。
じゃあ仮に、女の子しかいない社会があったらどうなるんだろうね?という会話もその時にしていました。そうすると、人を好きになるとか、上下関係や人間関係みたいなものはどうなるんだろうか。 女性同士の世界を描くことで、その社会の前提を再構築・再認識できるんじゃないか。それをこの映画の物語で実験してみました。
─本作では、主人公が惹かれていく「橋本佐保」という映画オリジナルのキャラクターをモトーラ世理奈さんがミステリアスに演じてます。主演の吉岡里帆さんとモトーラ世理奈さんの作中で描かれる関係も、一言では言い表せない不思議な温度と距離感ですよね。

千原:今の時代って、明確な結論や正解をすぐに求められる社会になってきている気がしていて。AIの目まぐるしい進化も後押しして、効率的に最短距離で答えに行き着くことが良しとされるような…。人間関係や人の感覚も、そうなりつつあるんじゃないかという焦燥感もあります。
原作にも映画にも、「うまく言葉に出来ないということは、今のところ、その素敵さは私だけのものだ」というセリフがあります。そんな「言葉に出来ない」「わからない」という完結しない感覚みたいなものを僕は肯定したいし大事にしたい。女性たちの物語にしたことで、その「わからなさ」にやさしく寄り添うストーリーにできたのではと思います。
セオリーを疑い、壊す。挑戦したのは「映画製作のデザイン」
─本作は、企画からキャスティング、宣伝にまつわるタイアップやコラボレーションまで千原さん自らが中心となり仕掛けていくインディペンデントな方法で製作されています。従来的な映画づくりだと、複数の企業が資金を持ち寄ってクオリティとリスクを共有するいわゆる製作委員会方式がスタンダードですが、それを選ばなかった理由とはなんでしょうか?
千原:まずそもそも初めてだったので、映画のつくり方がわからなかったという…。お金の集め方、キャストの揃え方、撮影の仕方、配給。何もかもわかってない状態でやろうと決めたので、まず最初は知り合いの映画プロデューサーの方と相談しました。そこで色々話してわかったのは、意外と映画って自由につくれないんだなってこと。作品は監督のものではなくて、あくまで出資者のもので、合意がなければ何一つ決めることができない。
脚本にしても、キャストにしても、音楽にしても、まずヒットさせやすいためのセオリーがあるんですよね。いわゆるマーケティング的な考え方。
─ハリウッド映画でもフォーマットの基本形があると言われていますよね。ストーリーのある時点で主人公が窮地に陥ったり、解決したり。
千原:さっきのAIの話じゃないですけど、そういう感動させるためのアルゴリズムってもう今の時代、大体分かってるんですよね。それじゃつまらないから、セオリーを全て取っ払って好きなように映画をつくりたい! ってなると、配給もついてくれない、お金出してくれる人も現れない、そもそもお客さんも入らないよ、っていう前提から、ものづくりがスタートしてしまう。
この作品も2019年に企画をスタートして、最初は製作委員会方式になりかけたんです。でも進めていくうちに違和感や動きづらさを感じるようになり、加えてコロナ禍もあった関係で、企画が一旦全てバラシになったんですよね。
その時点でスタートから2年くらい経ってしまっていましたが、その期間は映画製作の勉強をしたんだと割り切って。じゃあ、自分のやり方ってなんだろうと立ち返った時に、一番最初に僕は「映画製作をデザインする」という企画書をつくっていたんですよね。映画制作を、生業としてきたアートディレクターという立場でやってみようと。
─映画の映像だけではなく、映画製作そのものをデザインする。
千原:結果として『アイスクリームフィーバー』は脚本やディレクションは完全に自由にやりつつ、宣伝の部分だけ製作委員会方式をとりました。簡単に言うと、ブランドの広告を映画の俳優・世界観を使って僕がデザインを提供することをリターンとして、映画製作の資金を集めたんです。
例えば、劇中でも登場する猿田彦珈琲さんの広告を映画とタイアップする形で製作しました。猿田彦珈琲の恵比寿本店で映画のロケ地を再現したり、オリジナルのアイスを販売したり。広告には映画に登場したモトーラ世理奈さんをそのまま起用しています。
他にも映画の衣装提供をしていただいたアダストリア、ロケ地やエキストラでご協力いただいた岡山県の両備システムズ、心斎橋パルコ、Shibuya Fashio Weekなど、様々な領域のブランドや企業、店舗と連動したコラボレーションが多面的に発信できたのはこの映画ならではの特徴だと思います。



千原:また、今回はAからZ、数字までの「アイスクリームフィーバー・フォント」をオリジナルで一式デザインしました。コラボレーションするブランドや媒体にはそれを書体として使用して、アイスクリームフィーバーの世界観だと一目で分かるような統一感をディレクションしています。
─今回はポスターやキービジュアルも日本映画らしからぬ情報量を抑えたビジュアルに仕上がっています。やはりこちらも先ほど話されたセオリーへのカウンター意識があったのでしょうか?
千原:特に日本の映画ポスターはデザインやってる身からするとストレスを感じてしまうケースも少なくなくて。真ん中に主役がいて、左右にそれより小さく脇役が配置されていて、わかりやすいキャッチコピーが縦に入っていて…。加えて、この俳優さんはこの人より顔を大きくしないでください、みたいな変な決まりごとの中でデザインを強いられることもあります。
宣伝物だから、という理由はよく理解できますが、結果としてどれもこれも似たようなパターンに陥ってしまう。僕が映画にまつわるデザインに憧れてこの世界に惹かれたように、これからグラフィックデザインを志す人に、「この映画のポスターかっこいいな」と思われるようなものをつくりたかった。
今回のポスターも、普通に映画をつくったら絶対通らないデザインです。顔がだれかわかりづらいし、顔に文字がかかってるし、カナ表記もないし、キャッチコピーでストーリーもわからないし。でも、グッズやポスターやパンフレットを含めた、トータルの世界観が映画体験だと僕は思っているので、ビジュアルのクオリティを妥協せずに今回は自由にデザインしました。

─始めに挙げていただいた『E.T.』でもキービジュアルがパッと頭に浮かびますし、最近でもA24の映画はポスターデザインと映画が美しく同期している印象がありますよね。
千原:まさにA24はそうですね、作品が素晴らしいのは当然のことながら、デザインで世界観を引っ張ってる、底上げしてる部分がすごくあると思う。
映画だけでなくエンターテイメント全般に言えることですが、全てが過保護な表現というか、手にとってもらう・見てもらうために過剰な説明がいる社会になるのはつまらないですよね。そうではない方法で、どう表現すれば人が振り向いてくれるかは今後も実験的に取り組んでいきたいです。
─今回インディペンテントなつくりで実践できた面白さがある一方で、苦労した点や大変だった点も当然あったかと思うのですが、いかがでしょうか?
千原:でも意外とストレスはなかったですよ。徹夜で寝れないみたいな実作業の辛さはありましたけど。やっぱりクリエイティブをする上で一番苦労するのは、人を動かすってところなんですよ。自分の思った通りに人が動いてくれるかどうか。考えを理解してもらったり、違っていたら戦ったりしなきゃいけない時が一番大変です。
今回はスタッフィングもキャスティングも僕が一緒にやりたい人に電話やメールで自分で交渉して、脚本も撮影中まで自由に何度も描き直して。自分の好きなように100%できたので、つくる上でのストレスはゼロでしたね。

描き続けたいのは登場人物が生きる「街の質感」
─今作は渋谷を中心にしながら、リアルな街並みを舞台としてふんだんに使いながら撮影されていたのも印象的でした。
千原:最近の邦画って、あまり東京の街では撮らないらしいんですよ。大体地方に行って数ヶ月集中して撮影するとか、もしくはスタジオでメインとなる舞台をそっくりつくってしまうとか。そのほうが天候やスケジュールの制約を受けづらいですから。
でも、本物の街の質感っていうのはやっぱりセットでは出ない。それは普段から広告をやっていても思うことで、カメラの画角や照明のライティングも自由にやろうと思ったら、強いのはやっぱりロケなんですよ。
ウォン・カーウァイの『恋する惑星』も香港を舞台にしてるけど、いわゆるわかりやすい香港っぽいロケ地じゃなくて、登場人物たちが生きてる半径500mくらいをリアルに描いている質感がある。同じようにロケーションはこの映画の登場人物にとって重要なポイントだし、今後も自分が映画をつくる時は渋谷の街を使って撮影すると思います。それがオリジナリティにも繋がるのかなと。

─本作では高円寺の老舗銭湯・小杉湯も重要なロケ地として登場しますが、きっかけは現在進行している東急プラザ原宿「ハラカド」のプロジェクトでしょうか? 2024年春開業のハラカドの地下一階には小杉湯の2店舗目が入り、千原さんはハラカドのロゴデザインやクリエイティブラウンジのディレクションを手がけています。
千原:そうです、ハラカドの会議がきっかけで小杉湯代表の平松さんと出会いました。お会いして喋ってるうちに、 半径500メートルのコミュニケーションやまちづくりの考え方が僕と似ているなと感じて、この映画にも共感してもらえそうだなと。結果として場所を借りるだけでなく、銭湯の中で特別試写会イベントやらせてもらうなど立体的なコラボレーションに繋げてもらうことができました。
─次回作の構想もすでに練られているんでしょうか?
千原:あと2作ぐらいは、この『アイスクリームフィーバー』と地続きのような形で映画をつくりたいと思っています。渋谷を舞台に、自分の生活圏の風景や原体験を取り込んで、同じようなトーンと製作方法で。重ねて繰り返すことで、10年後や20年後に「これってアイスクリームフィーバーっぽい感じだよね」と自然に言われるような作品観を定着させたいです。
─面白いですね、それが監督としての「千原さんらしさ」にもなりつつ、街やブランドとコラボレーションした作品づくりは年数と回数を重ねていくほど強度が増していきそうです。
千原:多分、また何人か同じキャストには声をかけるし、同じ場所も出てくるかもしれないですね。
─最後に、『アイスクリームフィーバー』をこれから観る人に伝えたいことはありますか?
千原:この映画を見て、「自分も映画つくってみよう」と思ってもらえたらいいですね。僕も今回初めてやってみて、意外とつくれなくないということがわかりました。
自分の中でゴールが見えているならそこに向かうやり方はどういう動きをしたっていい。次の一歩を間違っちゃいけないと思いすぎないで、まっすぐな道じゃなくても、左右にはみ出して、何年かかったとしても、 ゴールさえ間違っていなければ、どんなやり方でもいいんだよということを伝えたいです。これは映画づくりに限らず、自分の夢や将来やりたいことでもそう。100人いたら100通りあっていいじゃん、っていう。この映画を観て、自分もまずはやってみようと感じてもらえたら嬉しいですね。
映画『アイスクリームフィーバー』Official HP
https://icecreamfever-movie.com/
株式会社 れもんらいふ Official HP
https://lemonlife.jp/